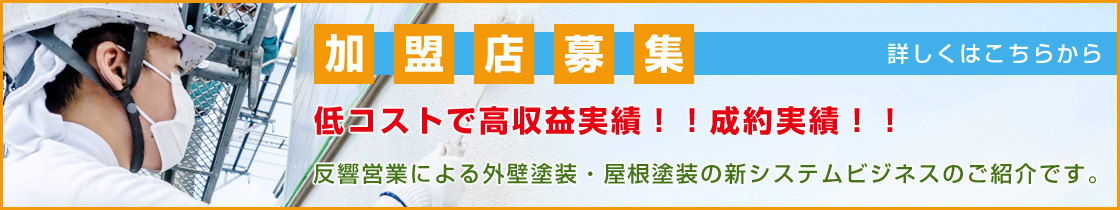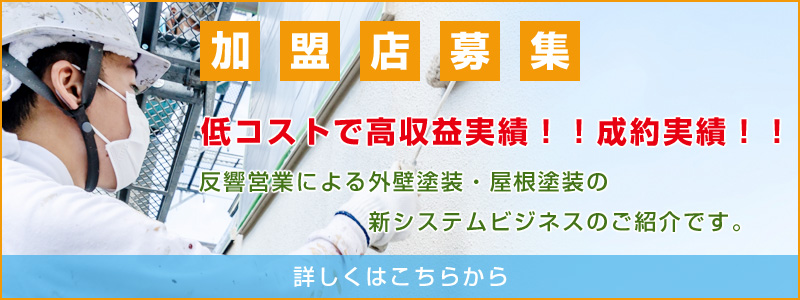屋根棟の部分が浮いていて強風の際に怖いから見て欲しいとご相談を頂き、調査致しました。
屋根棟の部分が浮いていて強風の際に怖いから見て欲しいとご相談を頂き、調査致しました。
 棟板金撤去後の写真です。先ず最初に棟板金を撤去致しました。
棟板金撤去後の写真です。先ず最初に棟板金を撤去致しました。
棟板金は釘やビスで貫板(木材)に固定されています。その為、既存の棟板金を固定している釘を外し、棟板金を慎重に撤去致します。
無理に外すと周囲の屋根材(スレートや金属)を傷つけてしまうことがあるため、注意が必要です。
固定を外したら、板金を手作業でゆっくり撤去します。
 棟貫板撤去後の写真です。
棟貫板撤去後の写真です。
棟板金を外すと、中にある木製または樹脂製の貫板が露出します。
そして釘やビスを外して貫板を取り外します。
解体中の注意点としては、下の防水紙や屋根材を傷つけないように注意が必要になります。
釘の抜き跡やサビなどがないかチェックし、屋根材やルーフィング(防水シート)に破れがないか確認を必ずします。
 棟材 樹脂製タフモック設置後の写真です。
棟材 樹脂製タフモック設置後の写真です。
タフモックとは、材質は樹脂でできており、腐らない・シロアリに強い・反りにくい・軽いという特徴があります。
こちらの棟材の寿命は約30年程の耐久性があるため人気の高い商品になります。(木製は10~15年)
屋根下地(野地板)に向けてステンレスビスでしっかり固定します。
注意点としましては、
・ビスの種類→ステンレス製or耐蝕性の高いものを使用する(普通の鉄ビスはNG)
・野地板が弱っていないか、ビスが効く状態かを確認してから設置する。
・長さが足りない場合は継ぎ目に隙間が出ないようにしっかり密着させる。
・特に棟の端部は雨水が侵入しやすい場所なので、板金とシーリングで処理必須となる。
 棟板金新設後の写真です。
棟板金新設後の写真です。
棟板金を必要な長さにカットし、接合部(重ね部)は50~100mm程度に重ねるのが基本となります。
また、端部(ケラバ側)は水切り形状に曲げ加工しておくと良いです。
棟板金のビスはステンレス製のパッキン付きビス(4.0×45~65mm)が主流となり、300~450mm間隔が目安です(強風地域ではさらに密に)
仕上げには、板金と板金の重ね部にコーキング(シーリング)処理をし、棟の端(ケラバ側)にも板金キャップor折り返し加工+シーリングをして完了です。
最終確認として、ビスが浮いていないか、板金が浮いていないか、シーリングが切れていないか、雨水の流れを邪魔する構造がないか、ゴミは落ちていないか、釘やビスは落ちていないか確認を忘れずに行います。